ダウン症候群は一般にもよく知られている染色体疾患のひとつです。最近では高嶋ちさ子さんのお姉さんがメディアに登場し、ご家族とのユーモアあふれる日常が紹介されるなど明るい側面に触れる機会も増えてきました。
その一方で、ダウン症候群と聞いて「育てていけるのだろうか」と不安を感じたり、出産を迷ったりする人がいるのも事実です。
2013年から日本でもNIPT(新型出生前診断)が始まり、妊娠初期に染色体疾患の可能性がわかるようになりました。選択肢が増えた一方で、妊婦さんやそのご家族が抱える悩みはより深く複雑になっていると感じます。
私は臨床心理士として、ダウン症候群と診断された妊婦さんやご家族と関わってきました。この記事では、実際に出会ったご家族の経験をもとに診断を受けたときの“こころの動き”をお伝えしたいと思います。

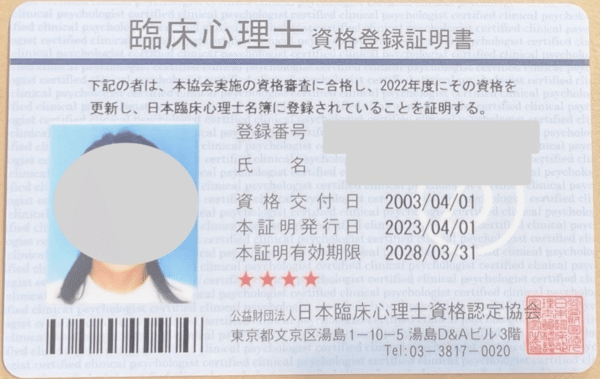
臨床心理士・公認心理師。産婦人科や小児科などの医療現場で15年以上にわたり、妊産婦さんへの心理支援に携わってきました。現在も妊娠期や産後の女性を対象に、心理面接やスクリーニングを行い、多職種と連携しながら周産期のこころのサポートに取り組んでいます。流産や死産など、喪失体験をされた方への心理的ケアにも力を入れ、ひとりひとりに寄り添った支援を大切にしています。
四十路!妊活記録のブログを運営しています。
ダウン症候群の特徴|知っておきたい身体的・発達的なポイント
染色体の変化によって起こる先天性疾患
人の体は「細胞」という小さな単位でできており、その中にある「染色体」は体のつくりや働きを決める設計図のようなものです。人は通常、46本(23対)の染色体を持っており、そのうちの1対(2本)は性別を決める性染色体(男性はXY、女性はXX)です。残りの22対(44本)は常染色体と呼ばれ、身体のさまざまな部分をつくる役割を担います。
21番目の常染色体が通常2本のところ、3本存在する状態を「21トリソミー」と呼び、これがダウン症候群の原因です。染色体が1本多くなることで、細胞内の遺伝情報が過剰となり、発達や知的機能に影響が現れます。
この特徴を報告したイギリスの医師ジョン・ラングドン・ダウン(John Langdon Down)の名前にちなんで「ダウン症候群」と名づけられました。
ダウン症候群は、染色体異常のなかでも最も頻度が高く、出生1,000人あたり1.5〜2人、約500〜600人に1人の割合で生まれるとされています。
なお、染色体異常がある胎児は流産率が高く、ダウン症候群のお子さんも例外ではありません。それだけに、さまざまなハードルを超えて生まれてくる命には、強い生命力を感じるという声もあります。
見た目や身体の特徴|筋緊張の弱さ・心疾患の合併が見られることも
ダウン症候群のお子さんには、目尻が少し上がっている、鼻すじが低めで鼻が小さく見える、舌が前に出やすいなど共通して見られる顔立ちの特徴があります。
また、多くのお子さんに筋緊張の低さ(体がふにゃっとやわらかい感じ)が見られ、ミルクを飲む力が弱かったり、歩き始めるまでに時間がかかることもあります。
心臓の病気やお腹の病気を持って産まれてくることもありますが、適切な治療とケアにより、以前よりも寿命は大きく延びています。20歳を超えることが難しいとされていた時代もありましたが、現在の平均余命は60歳を超えるまでになりました。
知的発達のペースと個性の豊かさ|成長はゆっくりでも着実に
ダウン症候群のあるお子さんは、知的発達がゆっくりなことが多く、新しいことを理解するのに時間がかかることがあります。ただ、丁寧に繰り返すことでしっかりと身につけていくことができます。
性格は人懐っこく、笑顔が多い子が多く、まわりの人を和ませる力をもっていると言われています。こだわりが強く、頑固に見える一面もありますが、それは好きなことにじっくり取り組む力でもあります。
芸術、音楽、身体表現などの分野で個性を発揮し、書道家、画家、ダンサーとして活躍している方もいます。
妊娠中に『陽性』と診断された妊婦さんの葛藤とその後の選択
臨床心理士の私が関わったダウン症候群と診断されたご家族のエピソードを、個人が特定されないように複数の事例をもとに構成した架空の事例としてご紹介させていただきます。
NIPT陽性と告げられたとき、妊婦さんが抱いた不安とその後の決断
「昔から慎重な性格で、何事も確認してから進めるタイプでした。NIPTも、“念のため”のつもりで受けたのですが、陽性という結果に大きなショックを受けました。」
検査を受ける前は「もし陽性なら中絶する」とご夫婦で話し合っていた方も、いざ結果を目の当たりにすると気持ちは大きく揺らぎます。
「頭では理解していたのに、決断ができませんでした。産む勇気も、中絶する覚悟も、どちらも持てなくて。どうしてこんなに迷ってしまうんだろう…。“私がこの子の命を止めてしまうの?”という思いが頭から離れませんでした。」
まわりからは「早くわかってよかったね」と声をかけられることもありますが、それが「中絶できてよかった」という意味に聞こえてしまうこともあり、妊婦さんの心に複雑な感情を残します。
最終的に、確定診断である羊水検査を経て、ダウン症候群と診断されたこの方は、赤ちゃんへの愛着と“障害のある子の親として生きていくこと”への不安。そのはざまで葛藤しながら、最後はご家族の意向に沿って中絶という選択をされました。
胎児エコーで異常の可能性を告げられたときの妊婦さんの不安と戸惑い
健診中にエコーの時間が長く「何かあるのかもしれない」と感じたという方もいます。
「心臓に異常があるかもしれない」と言われ、大きな病院への紹介状を受け取ったときには、不安と希望が入り混じっていたそうです。
「きっと大丈夫。大きな病院で見てもらえば、治療できるはず」そう思っていた矢先「この異常がある場合はダウン症の可能性がある」と説明されました。
「その瞬間、目の前が真っ暗になって、医師の話が耳に入ってきませんでした。帰宅してから、手が震えるのを感じながらスマホで情報を必死に検索しました。“そんなはずはない”と否定したくて探し続けたんです。」
検索して出てくる情報は、自分の心を落ち着かせてくれるものばかりではありません。
「まだ確定じゃないから」と言ってくれる夫の言葉も、当時の彼女には届きませんでした。
検査結果が出るまでの数週間、頭の中では「もしダウン症だったら…」という不安と「育てるのは無理。でも、命を諦めるのも無理」という堂々巡りが続いていたそうです。
【注釈】胎児エコーでは、首の後ろのむくみが厚い「NT肥厚」や、心臓の壁に小さな穴が見られる「心室中隔欠損症(VSD)」が見つかることがあります。これらはダウン症候群の赤ちゃんに多く認められる所見です。
羊水検査で確定した現実を前にして、心が揺れた妊婦さんの声
「7年ぶりの妊娠でした。予定外の3人目だったけど嬉しかったんです。お腹も大きくなり、上の子どもたちも赤ちゃんの誕生を心待ちにしている時に羊水検査でダウン症と言われました。この年齢で、障がいのある子を育てられるのか。この子のことで、他の子どもたちにまで迷惑がかかってしまいます。私達が死んだ後まで面倒をみなきゃいけなくなりますよね」
妊婦健診で赤ちゃんの心臓に病気がある可能性を指摘され、羊水検査を受けました。ダウン症候群と確定診断されたのは22週を過ぎた時期で、中絶は選べない段階でした。
怒りや悲しみは医療者に向かい「どうしてもっと早くわからなかったのか」と病院を責める気持ちにもなったそうです。
「でも、夫は“どんな子でも僕たちの子。大丈夫だよ”と受け入れてくれました。
上の子どもたちにも話すと、“いじめられたら僕たちが守るよ”と言ってくれて、涙が止まりませんでした。」
身近なママ友の「この年齢で授かるなんて奇跡だよ。何か言う人がいたら私が守るからね」という言葉にも、大きく励まされたと言います。
周囲の理解が一つの命を守ることに繋がったケースでした。
出産後に診断されたご家族が感じる衝撃と受容のプロセス
「普通に生まれたと思っていたのに…」という戸惑い
出産直後、ミルクの飲みが悪い、よく寝ている、抱きにくい、顔立ちがきょうだいと違うなど、「何かちょっと気になるな」と思っていたとき、医師から「念のため染色体検査をしましょう」と告げられることがあります。
「健康に生まれたと思っていたのに」と喜びに満ちていた気持ちが、一瞬にして不安に変わります。
検査結果が出るまでの間は、「そんなはずない」と否定する気持ちと、「もしそうだったらどうしよう」という不安とで揺れ続ける日々です。
NICUや医療現場での説明と、追いつかない心の整理
合併症の影響でNICUに入院し、手術が必要な場合もあります。医療者から次々と説明を受け同意書にサインをする中で「手術でダウン症が治るなら…」と漏らすお母さんもいます。
それは、障がいそのものではなく「この子の未来が安心であってほしい」という、親としての切実な願いの表れだと感じます。
喜びと不安が同時に押し寄せる育児のスタートライン
ようやく自宅に帰って育児を始めても、免疫機能が弱いため、感染症にかかりやすく夜間に救急受診することもよくあります。
そうしたなかで、日々の体調管理に神経を使いながらも、赤ちゃんの存在に「この子、かわいいな」「キュンとする」という感情が芽生えてくるお母さんもいます。
一方で、「もしこの世界に、この子と私たち夫婦だけだったら、もっと自由に愛せたかもしれない」と社会的な偏見や周囲のまなざしを気にしてしまう気持ちを語る方もいます。
里子や養子縁組されるご家族も
ダウン症候群の診断を受けたことで、特別養子縁組や里親制度の利用を検討されるご家族もいます。
- 里親制度:家庭で育てることが難しいお子さんを、一定期間他の家庭で育てる制度(法律上の親子関係はなし)。
- 特別養子縁組:裁判所の決定により、実親との法的関係を終了し、新たに親子関係を結ぶ制度(生涯の親子関係)。
私がカウンセリングを担当したご家族のなかにも「この子を育てるのは無理」と特別養子縁組を希望された方がいました。
あるお父さんは、「小学生の頃にダウン症の子をいじめてしまった。だからバチが当たったのかもしれない」と話してくれました。
その方は、自分の子どもに障がいがあることをどうしても受け入れられず、上の子がいじめられるのではないかと強く心配されていました。
お母さんは次第に赤ちゃんへの愛着が強まるなかで、夫の意見に従うべきか葛藤していました。離婚して一人で育てる道も考えたそうですが、経済的な現実から難しく、最終的には特別養子縁組という選択をされました。
臨床心理士からご家族へ伝えたいこと
妊娠中に「ダウン症の可能性がある」と言われたとき、たくさんの不安が押し寄せてくるのは当然のことです。
これまで“自分とは関係のない世界”だった障がいと向き合うことになり、頭では「誰もが排除されない社会が大切」と理解していても、自分の人生や家族の未来が変わるかもしれない現実に直面すると心は大きく揺れます。
病気や発達の遅れ、通院や療育への不安、仕事や経済的負担、社会の偏見…。
一度にたくさんのことを考え「こんな自分は冷たいのでは」と感じてしまう方もいます。
でも、それはとても自然な感情です。
正しさだけでは選べない。人生は、もっと複雑で、もっと個別なのです。
出産を決断した方も、中絶を選んだ方も、それぞれに悩み、葛藤し、泣いて考え抜いた末の選択です。
どちらが正しい、間違っているという話ではありません。
個人的には悩み苦しんだ末に出した決断なら、赤ちゃんもきっとわかってくれると信じたいです。
【参考文献】
1)竹内千仙:染色体疾患 – ダウン症候群を中心に -.治療 106(12): 1390-1394, 2024.
2)橋本洋子:NICUとこころのケア-家族のこころによりそって-.メディカ出版,2000
3) 永田雅子:別冊発達32 妊娠・出産・子育てをめぐるこころのケア.ミネルヴァ書房,2016
4)日本ダウン症協会HP

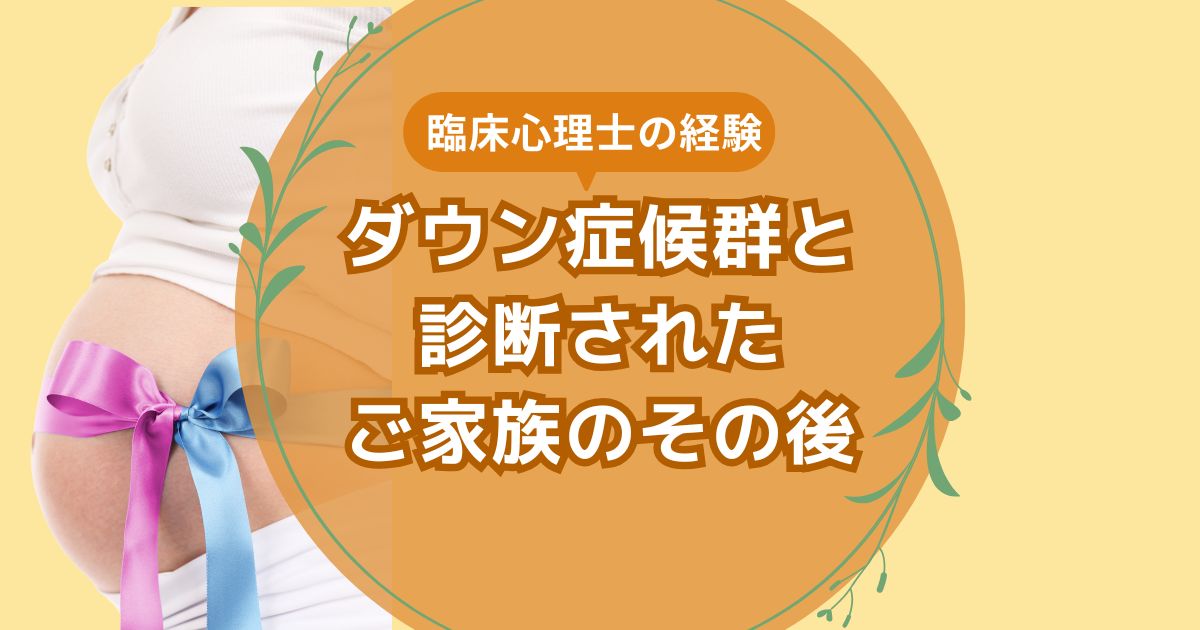

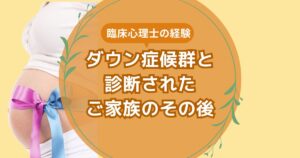

コメント